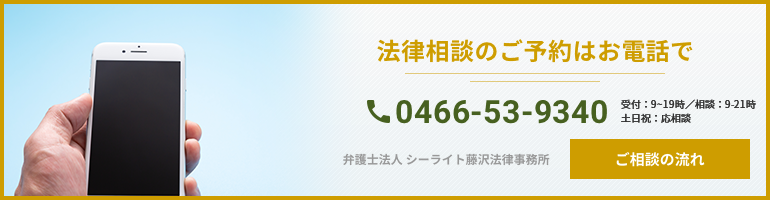在籍出向について
Contents
1.在籍出向とは?
在籍出向とは、労働者が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当の長期間にわたって当該他企業の業務に従事することをいいます。
その目的は、
- 技術指導等
- 能力開発、キャリア開発
- 景気悪化に伴う合理化(人員削減・雇用調整)
- リストラクチャリング(事業再構築)
等とさまざまです。
2.在籍出向を命じるにはどうしたらいいか?
出向は、出向元企業が労働者への労務提供請求権を出向先企業に譲渡するものであり、民法625条1項にいう「労働者の承諾」が必要となります。また、権利濫用になってはいけないことになります。
ケース
【X社長】:「弊社では、就業規則中に会社外の業務に従事するときは休職にする旨の休職条項があります。この休職条項は、弊社に在籍しながら他の企業の事業所で働くことを予定したものであるとして、出向命令の根拠にならないでしょうか?」
(1)「労働者の許諾」とは?
「承諾」といっても、
- 労働者の個別的な同意
- 労働協約や就業規則に基づく事前の包括的同意
等異なるレベルが存在し、どういったものが「承諾」として認められるかが問題となります。上記ケースで、最高裁は、就業規則や労働協約上の根拠規定、もしくは採用時の労働者の同意等の明示の根拠のない限り、出向命令が労働契約上予定されているとはいえない(日東タイヤ事件 最二小判昭48.10.19 労判189-53)として、「労働者の承諾」を認めませんでした。
したがって、明示の根拠が必要になります。
ケース
J社はコロナ不況のあおりをうけて、雇用調整する必要が生じた。Aは、新卒採用時からJ社につとめて10年になり、ここ4年ほどは人事部で働いている。Y人事部長は、Aを対象として以下の措置を講じた。
① Y人事部長「Aには、次は人事異動として人事部から営業部にうつってもらう」
② Y人事部長「Aには、次はJ社からK社へうつってもらう」
(2)明示の根拠だけで足りるのか?
上記ケース①②ではやはり印象が異なるかと思います。①J社内での部の移動は、ジョブローテーションの一環として受け入れやすいのに対して、②K社へ移ってしまうことは今までの人間関係、キャリアが一新されてしまい、不利益が生じる危険があります。
そこで、明示的な根拠だけではなく、
- 密接な関連会社間の日常的な出向であって、
- 出向先での賃金・労働条件、出向の期間、復帰の仕方などが出向期間等によって労働者の利益に配慮して整備されていて、当該職場で労働者が通常の人事異動として受容している(できる)ものであることを要する
と解釈されています。
そのため、上記ケース②では、
- J社とK社が同じグループの会社であって、頻繁に出向が行われている
- 賃金はJ社とK社で同水準である
- 出向の期間が限られている
等といった事情がなければ、出向が違法・無効となるおそれがあります。
(3)権利濫用になる場合とは?
出向命令権の濫用の有無は、
- 出向を命ずる業務上の必要性
- 人選の合理性(対象人数、人選基準、人選目的等の合理性)
- 出向労働者の職業上および生活上の不利益
- 当該出向命令に至る動機・目的等
を勘案して判断されます(リコー事件 東京地判平25.11.12 労判1085-19)。たとえば、退職勧奨を断った労働者全員を出向対象とした点で人選の合理性なしとされたもの(上記リコー事件)があります。
3.まとめ
出向は、前述のとおり、明示の根拠がなければ行うことはできず、さらに、通常の人事異動(配転)とは異なる配慮が必要になります。出向制度を導入したい、出向させたいと検討中の方は、弁護士にご相談ください。

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

最新記事 by 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所 (全て見る)
- メンタルヘルス不調が原因で問題行動・勤怠不良を繰り返す社員の解雇 - 2024年7月25日
- 電話工事に伴う電話・FAX不通のお知らせ - 2024年6月25日
- 取り返せなくなる前に!従業員による横領等の被害を回復する方法について解説 - 2024年4月30日
その他各種労働問題に関するその他の記事はこちら
- 人事異動は自由にできる?配置転換を拒否されてしまう正当な理由について
- 従業員を出勤停止にしたい!給与の扱いなどの注意点について
- 対策しておけばよかった・・・となる前に、中小企業は労務のリスクマネジメントを!
- 出向・転籍・配転を行うにあたって押さえておくべきポイント
- 育児介護休業法について押さえておくべきポイント(令和3年改正対応)
- 継続雇用制度
- 休職の仕組み
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- 従業員のSNSトラブルに対して企業の取るべき対応策
- 退職勧奨
- 同一労働同一賃金に向けた当事務所のサポートについて
- 同一労働同一賃金施行後の対応手順
- 同一労働同一賃金への対応ができなかった場合に生じる不利益
- 同一労働・同一賃金のメリット・デメリット
- 日本と海外との同一労働・同一賃金に対する考え方
- 同一労働同一賃金に関連した主たる法律の改正について
- 同一労働同一賃金とは