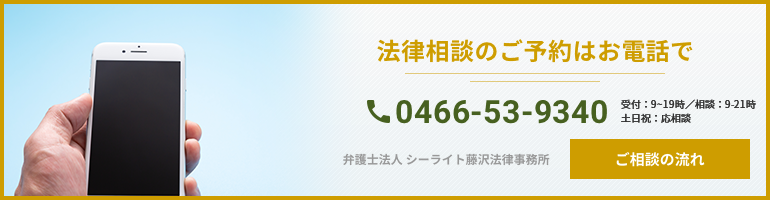従業員のSNSトラブルに対して企業の取るべき対応策
Contents
1 情報があっという間に拡散するので損害があっという間に拡大

ご存じのとおり限られた人しか閲覧できる設定にしていない限りSNS上に投稿された情報は瞬時に世界中の誰もが閲覧できる状況になります。そのため、目を引く投稿はあっという間に情報が多数の人に共有され、拡散され広まっていってしまいます。
従業員がSNSへ個人的に投稿した情報が拡散された結果、その内容によっては会社に大きな損害が発生するというケースも珍しくありません。
2 従業員のSNS利用による企業トラブルの具体例
情報漏洩のような形でトラブルが発生することがあります。例えば、従業員が何気なく撮影してSNSへ投稿した机の上のランチの画像に重要な企業秘密が記載された書類の一部が映りこんでいたため機密情報が漏洩したというような例です。
また、勤務先店舗に有名人がお忍びで来店したので記念撮影し、普段は自分のごく限られた友人しか見ていないからとTwitterに投稿したところ情報が拡散してしまったというような例です。
これらの場合、会社にさまざまな損害が発生することは間違いありませんが、現実的にはその被害回復を図ることが非常に困難です。特に、大事な顧客やその関係者から見放されてしまうなど、レピュテーションリスクは甚大です。
平成25年頃にはバイトテロという造語がメディアを賑わせました。バイトテロとは、アルバイト従業員が勤務先コンビニエンスストアの商品を陳列する冷凍庫の中に身体ごと入っているところをスマートフォンで撮影してSNSに投稿するなど、勤務先の設備や商品にふざけた行為をしている画像・動画を撮影してSNSに投稿することを揶揄したものです。
商品や備品を廃棄したり洗浄したりする必要が出てくるなど、財産的な損害が発生するばかりでなく、そのような店で買い物をしたくないと思われ、企業の評判を失墜させるものです。
そのほか、従業員が勤務先の会社や役員、従業員などを誹謗中傷する投稿をSNSに行うというケースや、社外の第三者や企業を誹謗中傷する内容の投稿をSNSに行うというケースなどがあります。
例えば前者については、新聞社の従業員が所属を明らかにした上で自身の個人的なホームページで、取材情報を使いながら社内批判や「適当に名前を考え」記事にしたなどの不適切な記述をした記事を掲載したという事例があります。
3 まずは情報・証拠の収集が必要
トラブルが発生してから時間がたてばたつほど被害が拡大していきます。そのため、企業として行うべきは迅速に行動することです。
まずはどのような行動をとるべきか整理しましょう。
一般的には、①情報の削除、②対外的対応、③当該従業員に対する対応、④再発防止策を講じることが挙げられます。
これらを適切に行うには情報・証拠の収集をしていく必要があります。
そのためにまずは調査にあたる人員を決めましょう。一般的には人事、法務、総務の人員がこれを担うことになると思います。
担当を決めた次に行うべきは、問題の情報が発信されているSNSサイトの調査です。
SNSサイトからは、当該情報やその周辺情報の画像を印刷したりデータ化して証拠化を行うとともに、情報を発信したであろう従業員の特定と拡散状況の調査も行いましょう。

次に、投稿をした従業員が特定できた、または概ね目星がついた場合は、当該従業員のPCや机、ロッカーなどの調査が考えられます。
このような場合であれば、調査に必要かつ合理的な範囲内に限り、会社からの貸与品については無断での調査も適法となりえますが、プライバシーの侵害となる可能性も否定はできません。
線引きの難しいところですので、就業規則に調査ルールを定めていない場合は可能な限り同意をとったうえで調査しましょう。
さらに、関係者への事情聴取、本人への事情聴取が必要となります。聴取した内容の正確性を保つため、5W1Hを意識した形で聴取内容をまとめましょう。
4 情報の削除をするには?
まずは当該従業員へ情報を削除するよう求めることとなります。
投稿者が特定できない、投稿者である従業員が削除を拒否するという場合もありえます。このような場合は、プロバイダ責任制限法に基づき当該Webサイトの管理者に対して情報の削除を請求しなければなりません。
しかし、この請求が認められるためには、
A)書き込みの削除が技術的に可能であり、
B)当該投稿によって権利侵害がなされていることを管理者が知っていた、または知ることができたと認められる相当な理由
が必要です。
削除請求になかなか応じてくれない管理者も珍しくなく、その場合は裁判手続が必要となります。そのため、削除を成功させるためには相当な知識・経験・労力が必要となるということを認識しておいた方がよいでしょう。
5 対外的な対応はするべきか?
対外的な対応では自社ホームページなどでのプレスリリースが一般的ですが、どのような場合でも必ずプレスリリースなどの対外的対応を行うべきなのかといえばそうではありません。
投稿された情報の内容が重大で世間的影響が大きいか否か、投稿された情報が早期に削除されてあまり拡散されなかったのかそれともかなり広範に拡散してしまっているのか、外部からの問い合わせが多数寄せられているかほとんどないか、など諸々の事情を考慮して決めるのが良いと思われます。
ただ公表すべき場合に、そのタイミングが遅れると会社の信用が大きく失われますので、注意が必要です。
6 問題を起こした従業員に対しては何ができるか?
投稿の内容や方法によっては労働者の立場としては懲戒処分の対象となり、民事上の責任としては損害賠償責任があります。内容によっては信用棄損・名誉棄損による刑事告訴による処罰もありえます。
ただ、従業員によって行われた不適切な投稿がすべて懲戒処分や損害賠償の対象となるかというとそうではありません。会社の秩序・規律維持に関係しなければ会社の懲戒処分権は及びませんし、会社に実害が生じ中れば損害賠償請求権も発生しません。また、就業規則の懲戒事由がきちんと整理されていなければ懲戒処分の対象とできないこともあります。
仮に懲戒処分の対象とできたとしても、懲戒解雇などの重い処分は後に無効となる可能性もありますし、損害賠償も全額の請求が認められるケースはまれであるばかりか従業員に賠償金を支払う資力がない場合も珍しくありません。
そのため、事案に応じた適切な処分を検討する必要があります。
7 再発防止策・・・最も重要なのは社員教育!
従業員のSNSトラブルを規制するうえで一番に思いつくのが社内ルール、つまり就業規則です。
まず、今後問題が起きた時にスムーズな調査をできるようにするため、会社の電子メールアドレスの私的利用禁止規定や私的利用の取り扱い、調査権限が会社にあることを就業規則に定めることをお勧めします。
次に、従業員を取り締まるための規定となりますが、企業が従業員に対して解雇や減給などの懲戒処分を行うには就業規則に定められた禁止行為に該当することが必要です。
就業規則の改定にはさまざまな制約や手続が存在します。インターネット環境が日々目まぐるしく進化してきていることを考えると、都度就業規則を細かく作り変えることは現実的ではありません。
また、多大な労力と時間をかけて就業規則を細かく作り直していっても従業員側がその内容を十分に理解していなければ何の意味もありません。

そのため、SNSトラブルを未然に防ぐには、社内外におけるSNSマナーを周知し、プライベートでの行いであってもマナー違反行為が自身にとって重大な不利益につながる可能性があることを周知するため、従業員向けの研修を行うことが最も効果的であろうと思われます。
特に、たくさんの実例を紹介したうえで、不注意でそのような投稿をした従業員がどのような目に遭うのか(考えられる懲戒処分の内容や損害賠償金の金額等)を伝えることで、従業員一人一人が自分事としてしっかり気を配り、マナーを守るようになっていくことが期待できます。
従業員向け研修の内容に説得力を持たせる目的で外部講師の起用をお考えの企業様におかれましては、お気軽にご相談ください。
SNSが絡む労務管理のご相談事例はこちら

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

最新記事 by 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所 (全て見る)
- メンタルヘルス不調が原因で問題行動・勤怠不良を繰り返す社員の解雇 - 2024年7月25日
- 電話工事に伴う電話・FAX不通のお知らせ - 2024年6月25日
- 取り返せなくなる前に!従業員による横領等の被害を回復する方法について解説 - 2024年4月30日
その他各種労働問題に関するその他の記事はこちら
- 人事異動は自由にできる?配置転換を拒否されてしまう正当な理由について
- 従業員を出勤停止にしたい!給与の扱いなどの注意点について
- 対策しておけばよかった・・・となる前に、中小企業は労務のリスクマネジメントを!
- 出向・転籍・配転を行うにあたって押さえておくべきポイント
- 育児介護休業法について押さえておくべきポイント(令和3年改正対応)
- 継続雇用制度
- 在籍出向について
- 休職の仕組み
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- 退職勧奨
- 同一労働同一賃金に向けた当事務所のサポートについて
- 同一労働同一賃金施行後の対応手順
- 同一労働同一賃金への対応ができなかった場合に生じる不利益
- 同一労働・同一賃金のメリット・デメリット
- 日本と海外との同一労働・同一賃金に対する考え方
- 同一労働同一賃金に関連した主たる法律の改正について
- 同一労働同一賃金とは
問題社員対応に関するその他の記事はこちら
- メンタルヘルス不調が原因で問題行動・勤怠不良を繰り返す社員の解雇
- 取り返せなくなる前に!従業員による横領等の被害を回復する方法について解説
- 他社事ではない!?従業員による横領等の原因や刑事・民事責任について解説
- 被害回復・お金の回収をしたい。弁護士さんも一緒にやってくれるの?
- 経営者必見-経理担当が架空口座へ送金している(全業種)
- 経営者必見-レジの中身とレシートがあわない(小売、飲食、医業)
- 2000万以上の横領被害を1か月半でスピード解決した事案
- 問題社員対応(解雇など)を弁護士に相談すべき3つの理由
- 問題を起こした従業員に対してはどのような懲戒処分ができるのか?
- 解雇にあたって使用者の義務とされる解雇予告についての注意点
- 問題社員を解雇する場合は要注意!解雇の種類とその選択
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応④ ~ハラスメントと会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応③ ~長時間労働と会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応① ~休職制度利用開始から自動退職までの対応~
弁護士コラムに関するその他の記事はこちら
- メンタルヘルス不調が原因で問題行動・勤怠不良を繰り返す社員の解雇
- 取り返せなくなる前に!従業員による横領等の被害を回復する方法について解説
- 他社事ではない!?従業員による横領等の原因や刑事・民事責任について解説
- 被害回復・お金の回収をしたい。弁護士さんも一緒にやってくれるの?
- 経営者必見-経理担当が架空口座へ送金している(全業種)
- 経営者必見-レジの中身とレシートがあわない(小売、飲食、医業)
- 長時間労働を指摘されるパターンと対策
- 事業場外労働時間制と専門型裁量労働制の「みなし労働時間制度」について
- 人事異動は自由にできる?配置転換を拒否されてしまう正当な理由について
- 従業員を出勤停止にしたい!給与の扱いなどの注意点について
- 不当解雇と言われトラブルになった場合の解雇の撤回について
- 対策しておけばよかった・・・となる前に、中小企業は労務のリスクマネジメントを!
- 普通解雇・懲戒解雇どちらを選ぶべき?懲戒解雇がお勧めできない3つの理由
- 問題社員対応(解雇など)を弁護士に相談すべき3つの理由
- 問題を起こした従業員に対してはどのような懲戒処分ができるのか?
- 解雇にあたって使用者の義務とされる解雇予告についての注意点
- 労働基準監督署による調査や是正勧告への対処方法
- 問題社員を解雇する場合は要注意!解雇の種類とその選択
- ストレスチェック制度について
- うつなどメンタル不調従業員との雇用契約は解消できるか
- 会社は健康診断の受診拒否や再検査を怠る従業員を懲戒処分できるか?
- 出向・転籍・配転を行うにあたって押さえておくべきポイント
- 労基署に最低賃金法違反の指摘を受けないよう気を付けるべきこととは?
- 育児介護休業法について押さえておくべきポイント(令和3年改正対応)
- 業務上労災にあった従業員の解雇制限
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応④ ~ハラスメントと会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応③ ~長時間労働と会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応① ~休職制度利用開始から自動退職までの対応~
- 残業代請求~名ばかり管理職とは?
- 副業・兼業の導入
- 自己都合退職の退職金
- 退職勧奨
- パートの有給休暇・有給付与義務について